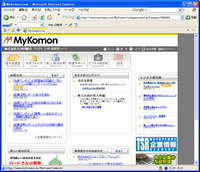出資額限度法人の出資払戻による相続

会計事務所のご紹介
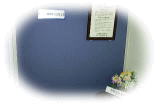
お問い合せ・アクセス
会計事務所の営業時間:
会計事務所の所在地:
〒156-0052
東京都世田谷区経堂1-12-5
第一吉良ビル3F
tel:03-3426-5485
fax:03-3426-5484
会計事務所へのメール:
日本公認会計士協会会員 :№12733
会計事務所開業
会計事務所長ご紹介

プロフィールはこちら
平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成23年12月現在)
1968/11 東京都世田谷区生まれ
1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
1991/04 大手監査法人就職
会計事務所開業

らくらく
電子申告に完全対応!

経営革新等支援機関
中小企業庁より認定
税額控除・補助金・融資など
が有利になります!
skypeで無料相談